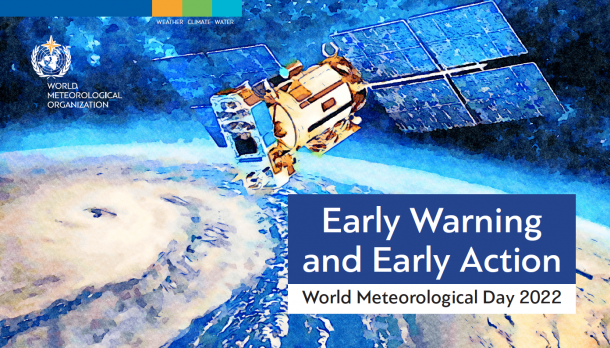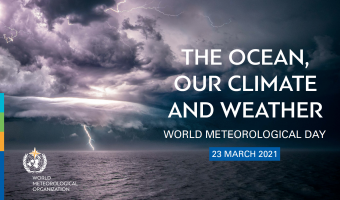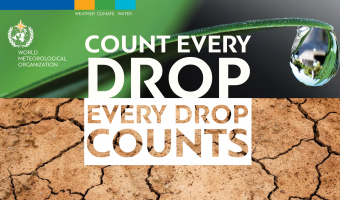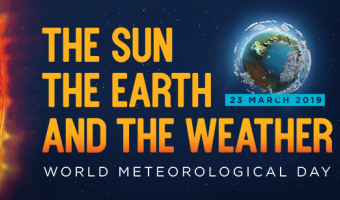世界気象デーについて
WMOは、昭和25年(1950年)3月23日に世界気象機関条約が発効したことを記念し、 毎年3月23日を「世界気象デー」として、気象業務への国際的な理解促進を目的にキャンペーンを行っています。 詳細は、WMOのウェブサイトをご覧ください。
世界気象デーのテーマ ~ 力を合わせて早期警戒のギャップを埋めよう(2025年)~
- 世界気象機関(WMO)は、1950年(昭和25年)3月23日に世界気象機関条約が発効したことを記念して3月23日を「世界気象デー」としており、毎年、気象業務への国際的な理解促進のためのキャンペーンを行っています。今年のテーマは「力を合わせて早期警戒のギャップを埋めよう」で、WMOでは、3月24日(月)にスイス・ジュネーブの本部で記念セレモニーを開催する予定です(詳細はWMO特設ページ参照)
- 気候変動により気象災害が激甚化する中、気候変動適応策の一つとして世界的に「防災」の重要性が高まっています。一方、開発途上国を中心に、警報を含む気象防災情報が必ずしも有効に活用されていない、その提供自体ができていないという状況を踏まえ、2022年(令和4年)にグテーレス国連事務総長の主導により、「国連早期警戒イニシアティブ『全ての人々に早期警戒を』(Early Warnings for All(EW4All))」が立ち上げられました。
- 本イニシアティブは、2027年(令和9年)までの5年間で世界中の人々が早期警戒システムにアクセスできることを目指し、開発途上国等の早期警戒システム構築を推進するものです。ここでいう「早期警戒システム」とは、警報等の防災気象情報を提供する仕組みのことで、WMOは気象の「観測と予報」に関する活動をリードする役割を担っており、開発途上国に対する技術的な支援や人材育成を通じて、早期警戒システムを構築しそれが人々に届くことを妨げている様々な課題や障壁(”ギャップ”)を埋めるための活動を行っています。
- なお、我が国は、WMOに1953年(昭和28年)に加盟しました。現在、気象庁は、気象衛星ひまわりの運用や、観測、通信、熱帯低気圧、気候等の様々な分野のWMOの地区センターを運用し、各国の気象業務を支援するための情報提供、技術協力等を行っています。アジア地区の主要な国家気象機関のひとつとして、これらの活動等を通じて、EW4Allの実現に向け引き続き国際貢献を行ってまいります。
- ソーシャルメディアで世界気象デーを話題にする場合、ハッシュタグ「#WorldMetDay」をご利用ください。
WMOでは、世界気象デーのテーマを毎年設定しています。近年のテーマについては以下をご覧ください。(画像はWMOウェブサイトより転載)
(過去のテーマ)
-
2018年 気象・気候への適切な備え
-
2017年 雲を理解する
-
2016年 より暑く、より乾いた、より雨の多い将来と向き合う
-
2015年 気候への対応のための気候情報
-
2014年 若者の未来に関わる天気と気候
-
2012年 未来を動かす - 天気・気候・水 –
-
2011年 気候、あなたのために。
-
2010年 安全と安心につくして60年
-
2009年 天気、天候、そして私たちをとりまく空気
-
2008年 より良い未来のために、私達の地球を観測する
-
2007年 極域の気象学 - 世界的な影響を理解する
-
2006年 自然災害の防止・軽減
-
2005年 気象・気候・水と持続可能な開発
-
2004年 情報化時代における気象・気候・水
-
2003年 将来の気候
-
2002年 異常気象に備えて
-
2001年 気象・気候・水へのボランティア