教育現場における気候変動の課題についてディスカッションを実施しその動画を公表しました
お知らせ掲示日
令和7年4月21日
概要
気象庁では、「教育現場における気候変動の啓発を考える」をテーマに有識者とディスカッションを行い、これを収録した動画を気象庁のYouTubeチャンネルに掲載しました。
ディスカッションでは、児童生徒が気候変動を自分事として捉えるには、教室の外でも気候変動問題に取り組む大人の姿を見せることが重要との意見も出ており、多くの方が気候変動問題を考えるきっかけとなるような内容ですので、是非ご覧ください。
本文
気象庁では、気候変動に関する情報の確かな理解と活用の促進を目的として、様々な取組を行っています。この度、地球規模の課題を扱う教育や啓発に取り組む方々と「教育現場における気候変動の啓発を考える」と題したディスカッションを行い、その様子を収録した動画を公表しました。
ショート動画(約1分):https://youtube.com/shorts/i4Nyui1e7_o
本編(約60分):https://youtu.be/gs–g2yG5Uk
ディスカッションにあたっては、予め、教育学を学ぶ大学生を対象にワークショップ(非公開)を開催し、気候変動教育における課題や気候変動をテーマとした授業案の検討を行っていただきました。ディスカッションでは、その成果を題材に
・「総合的な学習の時間」の活用や、教員間の連携による教科横断の授業構成による学びが、気候変動を自分事として深く考える機会となる。
・小学校高学年など早い段階から学び始めることで、地球規模の課題に対する意識を高める効果が期待できる。
・知識を深めることが気候変動に不安を感じるようになる恐れもある。児童生徒の気持ちを大切にしながら学ぶことや、教室の外でも小さいことから気候変動問題に取り組んでいる姿を大人が見せることで、希望を持たせることにつながる。
など、教育現場の実状を踏まえた効果的な学びや児童生徒の気持ち・意欲を大切にした啓発など、具体策を交えた意見がいくつも挙がりました。気候変動問題を自分事として捉えるきっかけとなるような動画になっていますので、是非ご覧ください。
気象庁は、一人ひとりが興味・関心のある分野を入口に、気候変動を自分事として捉えていただけるよう取り組んでいます。気候変動対策に関する社会的気運の醸成・理解促進に向け、引き続き、周知・広報活動を行ってまいります。
♦ディスカッションの概要
〇主催 気象庁
〇協力 国立研究開発法人海洋研究開発機構、日本大学生産工学部
〇後援 文部科学省、(一財)日本気象協会、地球ウォッチャーズ‐気象友の会‐
〇ディスカッションの参加者(※:パネリスト、#:ファシリテーター)
・荒川 知子※ 日本気象予報士会 常務理事
・永田 佳之※ 聖心女子大学 現代教養学部教育学科 教授
・市原 盛雄※ 海洋研究開発機構 海洋STEAM推進課 課長
・経田 正幸※ 気象庁 大気海洋部 気象リスク対策課 気候変動対策推進室 室長
・林 美穂# 日本気象協会
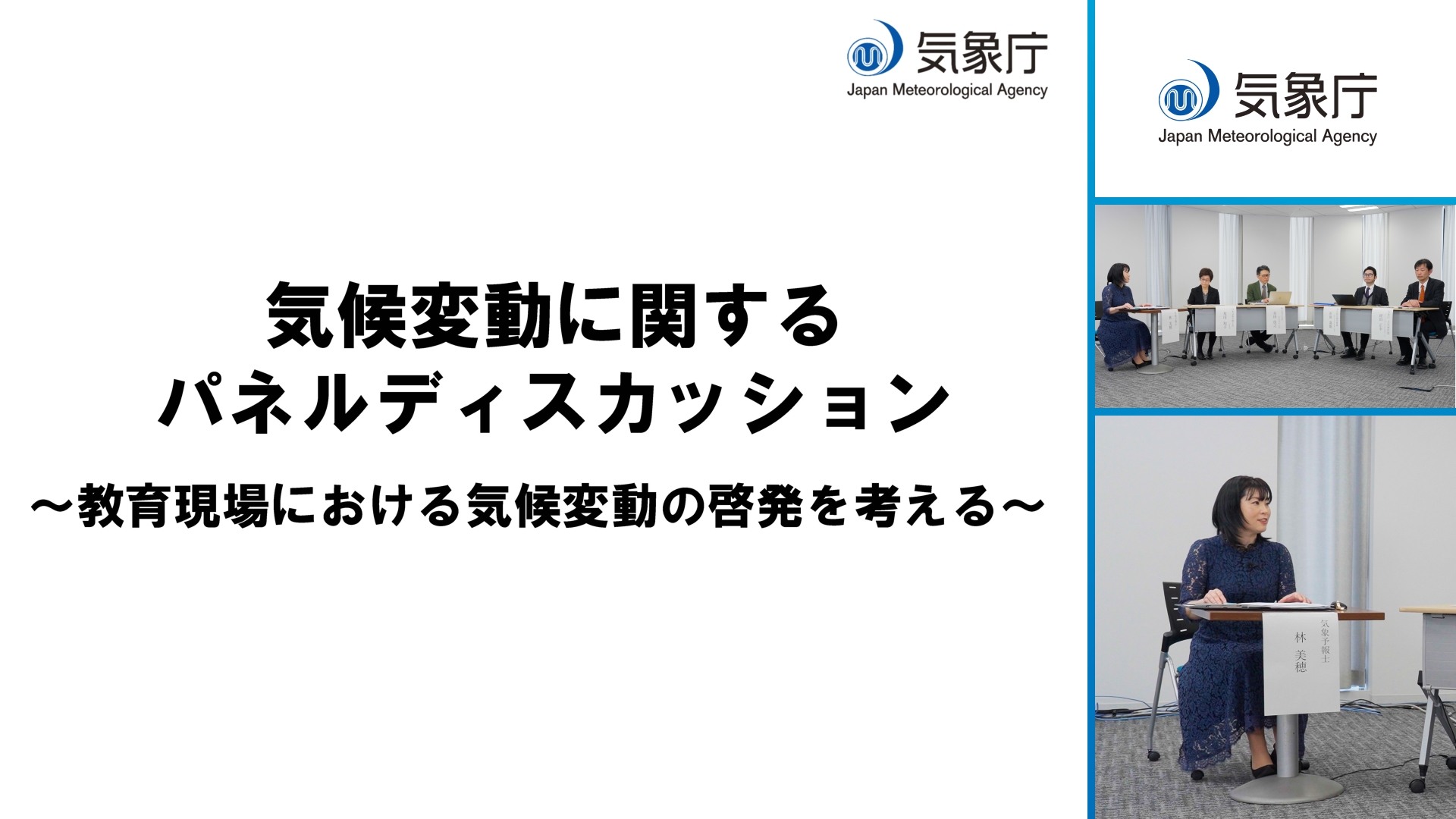
動画サムネイル

全体の様子
問合せ先
気象庁 大気海洋部 気象リスク対策課 気候変動対策推進室 大久保、苗田
電話:03-6758-3900(内線4112、4113)




