|
平成13年3月6日 気 象 庁 |
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
|
|
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第一作業部会による第三次評価報告書は、これまでに公表された評価報告を踏まえた上で、過去5年間の気候変化に関する調査研究から得られた新たな成果を取りこんでいる(脚注1)。同報告書のとりまとめと査読には、多くの国から千人近い科学者(脚注2)が参加した。 この政策決定者向けの要約(spm)は、2001年1月に上海において、各国政府によって承認されたものであり(脚注3)、気候システムに対する理解の現状を述べるとともに、予測される将来の変化とその不確実性の見積もりを示したものである。詳細は、この要約の元になる報告書本文に記述されている(出典注釈により、報告書の各章への参照を示す)。 *:本報告書は2001年4月のIPCC全体会合において最終的に結論づけられるため、現在の訳については今後変わる可能性がある。 脚注(1):IPCCが用いている「気候変化(climate change)」は、自然の変動または人間活動の結果のどちらによるものであろうとすべての気候の時間的変化を指している。これは、気候変動に関する枠組み条約における用法と異なっている。条約で用いられる「気候変化」は、地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接あるいは間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生じるものをいう。 (訳注1:climate change は条約の名称にならい「気候変動」と訳される場合が多いが、ここではvariation(変動)とchange(変化)を区別するため「気候変化」と訳した) 脚注(2):計122人の総括執筆責任者と執筆責任者、516人の執筆協力者、21人の査読編集者、337人の専門査読者。 脚注(3):99カ国の代表が、2001年1月17〜20日に上海で開催された第一作業部会第8回会合に出席した。 観測成果が増えたことによって、世界的な温暖化及び気候システムにおけるその他の変化についての全体像が明らかになっている第二次評価報告書の公表以降、現在及び過去の気候に関する新たな研究により追加されたデータ、データ解析の進歩、データに関するより厳密な品質評価、異なる出所からのデータ間の比較により、気候変化に関する理解が大きく進展した。地球の平均地上気温は、20世紀に約0.6℃上昇した ・地球の平均地上気温(陸域における地表付近の気温と海面水温の平均)は、1861年以降上昇している。20世紀中の気温の上昇量は、0.6±0.2℃(脚注4,5)(図1a)であった。この値は、1994年までを対象とした第二次評価報告書(脚注6)の見積もりより約0.15℃高い。これは、新たに加わった期間(1995〜2000年)が比較的高温であったこと、データ処理の手法が改良されたことによるものである。これらの数値は、都市のヒートアイランド効果を含む様々な補正がなされている。観測データによると、過去に大きな変動が存在した(例えば、20世紀中に起きた温暖化の大部分は、1910〜1945年及び1976〜2000年の二つの期間に発生した)。 脚注(4):大体の場合、気温の長期変化傾向(トレンド)は、単位期間あたり0.05℃単位に丸めてある。なお、トレンドが得られる期間は、データが利用できる期間に依存することが多い。 脚注(5):一般に、5%の統計上の有意水準が用いられ、信頼限界は95%である。 脚注(6):本要約では、IPCC第二次評価報告書を引用する際はSARと表記する。 (訳注2:ここでは、SARを「第二次評価報告書」と訳す) ・地球全体でみた場合、1861年以降の観測機器による観測記録の中では、1990年代は最も暖かい10年間であり、1998年は最も暖かい年であった可能性がかなり高い(脚注7)(図1a)。 ・北半球の代替データを用いた新たな解析によると、20世紀における気温の上昇は、過去1000年のどの世紀よりも大きかった(図1b)可能性が高い(脚注7)。また、北半球では、1990年代は最も暖かい10年間であり、1998年は最も暖かい年であった可能性が高い(脚注7)(図1b)。しかし、現在より1000年以上前の年平均気温や、1861年より前の南半球の大部分における状況は、利用可能なデータが少ないためよくわかっていない。 脚注(7):この「政策決定者向けの要約」と「全体要約」では、信頼度を判断する見積もりを示すのが適切な部分において、次の用語を用いる。「ほぼ確実(virtually certain)」(実現性が99%以上)、「可能性は(が)かなり高い(very likely)」(同90−99%)、「可能性は(が)高い(likely)」(同66−90%)、「どちらとも言えない(medium likelihood)」(同33−66%)、「可能性は(が)低い(unlikely)」(同10−33%)、「可能性は(が)かなり低い(very unlikely)」(同1−10%)、「可能性は(が)極めて低い(exceptionally unlikely)」(同1%未満)。詳細は個々の章を参照されたい。(どの用語も、おのおのの用法は脚注を参照すること) ・平均すると、1950年から1993年までの期間に、陸上における夜間の日最低気温は、10年あたり約0.2℃上昇した。これは、日中にあらわれる日最高気温の上昇率(0.1℃/10年)の約2倍になる。このため、中・高緯度地域の多くで、非凍結期間が長くなった。この期間の海面水温の上昇量は、陸上における平均気温の上昇量の約半分である。 (図1) 気温は、高さ8kmまでの大気において、過去40年間上昇してきた ・1950年代後期以降(高層気象観測用のラジオゾンデによる十分な観測がある期間)、地球の気温は、高さ8kmまでの大気でも地上でも同様に、10年あたり0.1℃上昇してきた。 ・1979年に衛星による観測記録が始まって以降、衛星と高層気象観測用のラジオゾンデの両観測ともに、高さ8kmまでの大気の地球の平均気温は10年あたり+0.05±0.10℃変化したのに対し、地球の平均地上気温は10年あたり+0.15±0.05℃と著しく上昇したことを示している。この気温の上昇量の差は、統計上有意である。また、この差は、主に熱帯と亜熱帯の地域で生じている。 ・高さ8kmまでの大気と地表付近の大気とでは、成層圏オゾンの減少、エーロゾルやエルニーニョ現象などによって受ける影響が異なる。このため、それぞれの気温トレンドは、短期間(例えば20年間)ならば互いに異なることがあり得ると予想することは、物理的に妥当である。加えて、空間的サンプリングの手法でもトレンドの差を説明できるが、この差は十分に解明されているわけではない。 雪氷面積は減少している ・衛星データによると、1960年代後期以降、積雪面積の約10%が減少した可能性がかなり高く(脚注7)、また、地上における観測によると、20世紀中に、北半球の中・高緯度域の湖沼や河川が氷で覆われる年間日数がおよそ2週間減った可能性がかなり高い(脚注7)。 ・20世紀には、極以外の地域で山岳氷河の後退が広範に見られた。 ・北半球の春及び夏の海氷面積は、1950年代以降、およそ10から15%減少した。この数十年、晩夏から初秋にかけての期間、北極の海氷の厚さは約40%減少し、冬の海氷の厚さもかなりゆっくりではあるが減少した可能性が高い(脚注7)。 地球の平均海面水位は上昇し、海洋の貯熱量は増加した ・潮位計データによると、20世紀に、地球の平均海面水位は0.1〜0.2m上昇した。 ・海洋表層の水温観測データが十分に得られる1950年代後期以降、地球の海洋貯熱量は増加してきた。 変化は、気候の他の注目すべき側面にも現れている ・降水量は、北半球の中・高緯度の陸域の大部分において、20世紀に、10年間あたり0.5〜1%増加した可能性がかなり高く(脚注7)、さらに、熱帯(北緯10度から南緯10度)の陸域において、降水量が10年間あたり0.2〜0.3%増加した可能性が高い(脚注7)。熱帯域における降水量の増加は、過去20〜30年では明瞭でない。また、降水量は、北半球の亜熱帯(北緯10度から30度)の陸域の大部分で、20世紀中に10年あたりおよそ0.3%減少した可能性が高い(脚注7)。北半球とは対照的に、南半球では、緯度平均を広く取れば、これに匹敵する系統的な変化は検出されていない。 海洋上の降水のトレンドを立証するに十分なデータはない。 ・20世紀後半、北半球中・高緯度域においては、大雨の発現頻度が2〜4%増加した可能性が高い(脚注7)。大雨事例の増加は、大気中の水蒸気、雷雨活動、大規模な低気圧の活動の変化など、多くの原因から生じ得る。 ・20世紀中に中・高緯度の陸域における雲量は2%増加した可能性が高い(脚注7)。このトレンドは、大部分の地域で、気温の日較差が減少したという観測結果と良い相関がある。 ・1950年以降、極端な低温の発現頻度は減少し、極端な高温の発現頻度は小幅に増加した可能性がかなり高い(脚注7)。 ・エルニーニョ現象(訳注3)(エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、熱帯及び亜熱帯の大部分と所により中緯度域でも、降水や気温の地域的変動に影響する)は、1970年代中期以降、それ以前の100年に比べて、発現頻度、持続期間、強度が増大している。 (訳注3:原文は、Warm episodes of the El Nino-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon(エルニーニョ・南方振動(ENSO)の暖水期)であるが、我が国では、これを「エルニーニョ現象」と表現することが一般的であるため、この表現を用いる。なお、ENSOの冷水期は、「ラニーニャ現象」と表現する。) ・20世紀(1900〜1995年)において、厳しい干ばつあるいは著しい多雨が発生した陸上の地域は、小幅な増加があった。多くの地域で、これらの変化は、ENSOがエルニーニョ現象側にシフトするような十年及び数十年規模の気候の変動性に支配されている。 ・アジア及びアフリカの一部のように、干ばつの発現頻度と厳しさが、ここ数十年で増加したことが観測されているところがある。 気候の注目すべき側面のいくつかは変化していないように見える ・地球のいくつかの地域、主に南半球の海洋と南極大陸の一部では、この数十年温暖化していない。 ・南極の海氷面積は、信頼できる衛星観測が得られる1978年以降、有意なトレンドは見られない。 ・地球全体で見た場合、熱帯低気圧及び温帯低気圧の強さや発生頻度の変化は、10年〜数十年変動に支配され、20世紀においては有意なトレンドは見られない。特に温帯域における低気圧の活動の変化については、相反する解析結果があることから、最終的な結論を導くことは難しい。 ・竜巻、発雷、ひょうの発現頻度の系統的な変化については、限られた地域の解析では明らかでない。 人間活動による温室効果ガス及びエーロゾルの排出は引き続き大気を変化させ、気候に影響を与える気候の変化は、気候システム内部の変動と外部因子(自然起源と人為起源の両者)の結果として起こる。気候に対する外部因子の影響については、放射強制力という概念を使っておおよそ比較しうる(脚注8)。温室効果ガス濃度の増加などによって生じる放射強制力は、正の値を持ち、地表を暖める方向に働く。ある種のエーロゾル(大気中の微粒子)の増加によって生じる放射強制力は負の値を持ち、地表を冷やす方向に働く。太陽放射の変化や火山噴火のような自然起源の因子も放射強制力をもたらす。これらの気候の変動因子及びその時間変化を特徴づけることは(図2参照)、自然の変動と関連させて過去の気候変化を理解し、将来起こりうる気候変化を予測するために必要である。図3は、大気組成物質の濃度増加及びその他のメカニズムによる放射強制力の現在の見積もりを示す。脚注(8):「放射強制力」とは、地球―大気システムに出入りするエネルギーのバランスを変化させる際、ある因子が持つ影響力の尺度であり、気候を変化させる可能性の大きさを示す。放射強制力は、1平方メートルあたりのワット数(Wm-2)で表される。 (図2) 人間活動の結果、大気中の温室効果ガスの濃度及びその放射強制力は増加を続けている ・大気中の二酸化炭素(CO2)濃度は、1750年以降31%増加した。過去42万年間で現在の二酸化炭素濃度を超えたことはなく、過去2000万年でも超えなかった可能性が高い(脚注7)。現在の二酸化炭素濃度の増加率は、少なくとも過去2万年で例のない高い値である。 ・過去20年間の人為起源による二酸化炭素の大気への排出のうち、約4分の3は化石燃料の燃焼によるものである。残りの大部分は土地利用の変化、とりわけ森林減少によるものである。 ・今のところ、人為起源による二酸化炭素の排出量の約半分が海洋と陸域で吸収されている。1990年代、陸域では、人為起源の二酸化炭素の吸収は、森林減少による二酸化炭素の放出を上回っている可能性がかなり高い(脚注7)。 ・過去20年で、大気中の二酸化炭素濃度の年増加率は、約1.5ppm(0.4%)(脚注9)である。1990年代の年々の増加量は、0.9ppm(0.2%)から2.8ppm(0.8%)の間で変動した。この変動の大部分は陸域と海洋での二酸化炭素の吸収・放出に気候の変動(例えばエルニーニョ現象)が及ぼす影響によるものである。 脚注(9):ppm(100万分の1)、ppb(10億分の1)は乾燥空気の全分子数に対する温室効果ガスの分子数の割合である。例えば、300ppmは、乾燥空気の分子100万個中に温室効果ガスの分子300個があるということである。 ・大気中のメタン(CH4)濃度は、1750年以降1060ppb(151%)増加し、さらに増加を続けている。過去42万年間で、現在のメタン濃度を上回ったことはない。メタン濃度の年間の増加は、1980年代と比べ1990年代にはゆるやかなものとなり、かつ変動しやすくなった。現在のメタン排出量の半分強が、人為起源(例えば、化石燃料の使用、畜牛、米作、埋立)である。これに加え、近年、一酸化炭素(CO)の排出がメタン濃度の増加の原因になっていることがわかってきた。 ・大気中の一酸化二窒素(N2O)濃度は、1750年以降、46ppb(17%)増加し、現在も増加を続けている。少なくとも過去1000年間で、現在の一酸化二窒素濃度を上回ったことがない。現在の一酸化二窒素排出量の約3分の1は、人為起源(例えば、農耕地土壌、畜牛、化学工業)である。 ・オゾンを破壊するとともに、温室効果も持つガスであるハロカーボン(例えば、CFCl3、CF2Cl2)の多くは、その大気中濃度が、1995年以降、モントリオール議定書及びその改正による規制の下での排出削減に応答して、増加がゆるやかになるか、あるいは減少している。しかしながら、これらの代替物質(例えば、CHF2Cl,CF3CH2F)もまた温室効果ガスである上、この他の合成化合物の中にも温室効果ガスがあり(例えば、パーフルオロカーボン(PFCs)や六フッ化硫黄(SF6))、いずれの物質もその大気中濃度は現在増加している。 ・1750年から2000年までの温室効果ガス全体の増加による放射強制力は2.43Wm-2と見積もられる。この内訳は二酸化炭素1.46Wm-2、メタン0.48Wm-2、ハロカーボン0.34Wm-2、一酸化二窒素0.15Wm-2である(図3参照。図には不確実性も示している)。 ・1979年から2000年までに観測された成層圏オゾン層の破壊に起因する放射強制力は、負の値(−0.15Wm-2)であったと見積もられる。現在のハロカーボンの規制が完全に実施されると仮定すれば、ハロカーボンによる放射強制力は低減することが見込まれるだけでなく、21世紀にオゾン層が回復するにつれて、成層圏オゾンの破壊で生じる負の値の放射強制力もゼロに近づくことが見込まれる。 ・対流圏のオゾン総量は1750年以降36%増加したと見積もられている。これは、いくつかのオゾン生成ガスの人為起源による排出によるものが主であり、放射強制力にして0.35Wm-2に相当する。オゾンの放射強制力は地域によって大きく変わり、二酸化炭素のような長寿命の温室効果ガスと比べて、排出量の変化にすばやく応答する。 (図3) 人為起源のエーロゾルは短寿命であり、大部分は負の放射強制力をもたらす ・人為起源のエーロゾルは、主として化石燃料とバイオマスの燃焼から発生している。これらの発生源はまた大気の質の悪化や酸性沈着にも関与している。 ・第二次評価報告書以降、エーロゾルが放射に果たす直接的な役割について、その種類別に理解が進んできた。エーロゾルによる直接的な放射強制力は、例えば、硫酸塩では−0.4Wm-2、バイオマス燃焼によるエーロゾルでは−0.2Wm-2、化石燃料燃焼による有機炭素では−0.1Wm-2、化石燃料燃焼によるすすでは+0.2Wm-2と見積もられる。エーロゾルの直接的な効果全体やその時間変化の定量化に対する信頼性は、先に挙げた温室効果ガスの場合に比べてかなり低い。また、エーロゾルの分布は、地域によりかなり変動するとともに、排出量の変化にすばやく応答する。 ・エーロゾルは、直接的な放射強制力に加え、雲に対する効果を通じて、間接的な放射強制力も持っている。この間接的な効果は、その程度は非常に不確実であるものの負の値の放射強制力であり、現在、この効果に関して、より多くの証拠が集まっている。 自然起源の因子は、過去100年間では放射強制力にあまり影響していない ・太陽放射の変化に起因する放射強制力は、1750年以降で約+0.3Wm-2と見積もられ、その大部分は20世紀前半に生じた。1970年代後期以降、衛星の観測機器により、11年の太陽活動周期による小さな振動を観測している。気候に及ぼす太陽活動の影響を増幅させるメカニズムが提案されてきたが、今のところ厳密な理論や観測による裏付けを欠いている。 ・爆発的な火山噴火による成層圏エーロゾルに起因する放射強制力は負の値であり、数年間持続する。いくつかの大規模な噴火が1880年から1920年にかけてと、1960年から1991年にかけて起こった。 ・2つの主要な自然起源の因子(太陽変動と火山性エーロゾル)による放射強制力の複合的な変化は、過去20年間、そしておそらく過去40年間は、負の値であったと見積もられる。 将来の気候を予測するモデルの能力の信頼性が増してきたフィードバックと地域的特徴を詳細に見積もるために、物理に基づいた高度な気候モデルが必要である。そのような気候モデルは、気候の全ての側面を再現できるわけではない(例えば、地上−対流圏温度差について、観測された1979年以降のトレンドを未だ十分に説明できない)し、とりわけ、雲、そして雲と放射やエーロゾルとの相互作用に関しては不確実性がある。それにもかかわらず、気候モデルがある程度の空間・時間スケールの気候を一定の性能で再現したことから、将来の気候に関する有用な予測を提供し得るという点でモデルの信頼度は改善された。・水蒸気、海氷力学及び海洋熱輸送など、気候の諸過程の理解とその気候モデルへの組込みは進展した。 ・最近のいくつかのモデルは、以前のモデルで用いられていた、大気と海洋の間で交換される熱量や水に関する人工的な調節をしなくとも、現在の気候を十分再現している。 ・自然起源及び人為起源の放射強制力の見積もりを含むモデル計算では、20世紀の地上気温で観測された大きなスケールの変化を再現する(図4)。いくつかの付加的な過程や放射強制力からの寄与は、モデルに含まれていなかったこともありうるが、 モデルと観測は、大きなスケールで一致しており、このことは与えられた排出シナリオの下で次の数十年間に予測される気温上昇率をモデルのみで独立してチェックすることを可能にしている。 ・選定した期間の過去の気候についてだけではなく、ENSO、モンスーン及び北大西洋振動のモデルによる再現性が、いくつかの面で改善された。 近年得られた、より強力な証拠によると、最近50年間に観測された温暖化のほとんどは人間活動によるものである第二次評価報告書では、「証拠を比較検討した結果、識別可能な人為的影響が地球全体の気候に現れていることが示唆される」と述べられた。同報告書はまた、人為起源のシグナルは、依然として自然起源の気候変動というバックグランドから読み取れる程度のものであると述べた。同報告書の公表以降、特に、異なる外的影響に対する応答を識別し定量化することに関して不確実性が減少した点で進歩があった。 同報告書で確認された不確実性の多くは、いまだにある程度残っているものの、最新の結論は、あらたな証拠と理解の進展によって裏付けられている。・より長期間の気温の記録が、より綿密に調べられるとともに、新しいモデルによる変動の見積もりがなされている。現在のモデルの見積もりによれば、過去100年にわたる温暖化が、気候システムの持つ内的な変動のみによる可能性はかなり低い(脚注7)。復元された過去1000年間の気候データ(図1b)によっても、この温暖化は異常であったことが示されるとともに、これが自然起源のみによる可能性は低い(脚注7)ことも示される。 ・自然起源及び人為起源の放射強制力に対する気候の応答が新たに見積もられ、さらに新しい検出技術が適用された。検出及び原因特定に関する研究により、人為起源のシグナルが過去35〜50年間の気候の記録から一致して見出されている。 ・自然起源の放射強制力のみに対する応答(すなわち、太陽放射の変動や火山噴火に対する応答)を調べるシミュレーションでは、20世紀後半の温暖化は説明できない(例えば図4a参照)。一方、このシミュレーションによると、自然起源の放射強制力が20世紀前半に観測された温暖化に寄与していたこともありうる。 ・人為起源の硫酸エーロゾルと自然起源の因子(火山や太陽放射)による放射強制力の不確実性にもかかわらず、温室効果ガスによる過去50年の温暖化は人為起源とみなすことができる。人為起源の硫酸エーロゾルによる放射強制力は、不確実性はあるが、この期間は負の値であり、それゆえ温暖化を説明できない。この期間のほとんどでは、自然起源の放射強制力の変化は負の値と見積もられ、この変化によって温暖化を説明できる可能性は低い(脚注7)。 ・現在は、モデルで再現された変化と観測記録を比較する、気候変化の検出及び原因特定の研究では、外的な放射強制力に対するモデル応答の大きさの不確実性、とくに気候感度の不確実性によるものを考慮できる。 ・これらの研究の大部分は、最近50年では、見積もられた温室効果ガス濃度の増加だけによる気温の上昇量と上昇率は、観測された気温の上昇量と上昇率に相当するか、それよりも大きいことを見出した。さらに、温室効果ガスと硫酸エーロゾルの両方を考慮したモデルによる見積もりのほとんどがこの期間の観測と矛盾していない。 ・図4cで示されるように、上記全ての人為起源及び自然起源の放射強制力の因子を複合させると、過去140年間のモデル計算と観測が最もよく一致することが分かった。このことは、観測された変化は、モデルに組み込まれている放射強制力によって表せることを示すが、これは他の放射強制力も寄与する可能性を排除するものではない。 (図4) 新しい証拠に照らすと、残された不確実性を考慮しても、過去50年間に観測された温暖化の大部分は、温室効果ガス濃度の増加によるものであった可能性が高い(脚注7)。 さらに、20世紀の温暖化は、海水の熱膨張と陸氷の広範な消失を通じて、観測された海面水位上昇にかなり寄与した可能性がかなり高い(脚注7)。現在、様々な不確実性の範囲内で、観測データとモデルによる予測とは、20世紀の海面水位上昇に顕著な加速が見られないことで一致している。 21世紀を通して、人間活動が大気組成を変化させ続けると見込まれるIPCC排出シナリオに関する特別報告書(SRES)に掲載された排出シナリオを基に、モデルを使用して、温室効果ガスとエーロゾルの大気中濃度、さらには将来の気候について予測を行った(図5)。SRESシナリオは、第二次評価報告書で用いられたIS92シナリオに最新の状況を反映させたもので、図5では、比較のためにIS92シナリオによる予測が示されているものもある。温室効果ガス ・化石燃料の燃焼による二酸化炭素の排出が、21世紀の間、大気中の二酸化炭素濃度のトレンドを支配することはほぼ確実である(脚注7)。 ・大気中の二酸化炭素濃度が増加するにつれて、人為起源の二酸化炭素が海洋及び陸域により取り込まれる割合が減少することになる。モデルでは、陸域と海洋に関わる気候フィードバックの正味の効果として、海洋及び陸域の両方で二酸化炭素の取り込み量が減少し、このため、大気中の二酸化炭素濃度はさらに増加すると予測される。 ・炭素循環モデルによると、2100年までに大気中の二酸化炭素濃度は、図5bに示すとおり、SRESシナリオの代表例として用いたシナリオに対し540〜970ppmになると予測されている(1750年の濃度である280ppmよりも90〜250%の増加)。この予測結果は、陸域及び海洋についての気候フィードバックを考慮したものである。特に陸域生態系についての気候フィードバックに関して不確実性があるため、シナリオ毎に−10〜+30%の誤差が考えられることから、全体の予測幅は490〜1260ppm(1750年の濃度よりも75〜350%の増加)となる。 ・土地利用の変化が、大気中の二酸化炭素濃度に影響することもありうる。もしこれまでの歴史上の土地利用の変化に伴って放出された炭素の全てが、例えば再植林によって21世紀中に陸域生態系に戻されると仮定すると、二酸化炭素濃度は40〜70ppm減少する計算になる。 ・二酸化炭素以外の温室効果ガスの濃度が2100年までにどのくらい変化するかについてのモデルの計算結果は、SRESシナリオの代表例として用いたシナリオ毎に大きく異なり、2000年での値を基準とした場合、メタンの変化量は−190〜+1970ppb(現在の濃度は1760ppb)、一酸化二窒素は+38〜+144ppb(現在の濃度は316ppb)、対流圏のオゾン総量は-12〜+62%であり、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)及び六フッ化硫黄(SF6)の濃度については、非常に広い幅で予測されている。シナリオによっては、対流圏オゾン総量がメタンと同程度の放射強制力を持つとの結果が出ており、北半球の大半の地域では、大気の質の目標達成が脅かされかねない。 ・温室効果ガスやその濃度に影響を及ぼすガスの排出を削減させることは、放射強制力を安定化させる上で必要となる。人為起源の温室効果ガスで最も重要な二酸化炭素については、例えば、炭素循環モデルによる計算によると、大気中の二酸化炭素濃度を450、650及び1000ppmで安定化させるためには、人為起源の二酸化炭素の排出量をそれぞれ数十年、約100年及び約200年以内に1990年のレベル以下にした上で、その後着実に減少させ続けることが必要となる。最終的には、二酸化炭素の排出量を現在に比べてごくわずかなレベルにまで減少させる必要がある。 エーロゾル ・SRESシナリオでは、人為起源のエーロゾル(例えば図5cに示す硫酸エーロゾル、バイオマス起源エーロゾル、黒色炭素エーロゾル及び有機炭素エーロゾル)の量が、化石燃料の使用量や汚染物質の排出抑制に関する政策次第で増加または減少する可能性が考慮されている。 さらに、自然起源のエーロゾル(例えば海塩、砂ぼこり、及び硫酸及び炭素エーロゾルの生成に影響を及ぼす放出物)は、気候変化のひとつの結果として増加することが予測されている。 21世紀における放射強制力 ・SRESシナリオのうち代表例として用いられたシナリオでは、温室効果ガスによる地球の平均放射強制力は、2000年を基準とした場合、21世紀全体にわたって増加し続けることになる。この中で二酸化炭素による放射強制力の割合は、半分を少し超える程度から約4分の3にまで増加すると予測している。エーロゾルによる直接的及び間接的な放射強制力を足し合わせたものの変化は、二酸化炭素に比べてその大きさは小さなものになると予測される。 地球の平均気温と平均海面水位は、IPCC SRESシナリオに基づく予測結果の全てで、上昇する将来の気候を予測するために、将来ばかりでなく過去の温室効果ガスとエーロゾルの排出をモデルの中に取りいれている。したがって、予測結果は、現在までの温暖化の見積もりと過去の排出が将来の温暖化に及ぼす影響をも含んでいる。気温 ・地球の平均地上気温は1990年から2100年までの間に1.4〜5.8℃上昇すると予測される(図5d)。この結果は、いくつかの気候モデルを用いた、35のSRESシナリオによる全ての予測の範囲の幅である(脚注10、11)。 ・予測される気温の上昇量は、6通りあるIS92シナリオに基づく第二次評価報告書の時の上昇量(1.0〜3.5℃)よりも大きくなっている。予測された気温の上昇量が高くなり、また、その予測の幅が広がったのは、主として、SRESシナリオにおける二酸化硫黄の排出量の予測がIS92シナリオに比べて下方修正されていることによる。 ・予測された気温上昇率は、20世紀に観測されたものよりもはるかに大きく、古気候のデータから、少なくとも過去10,000年の間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性がかなり高い(脚注7)。 脚注(10):物理に基づく高度な気候モデルは、将来の気候変化を予測するための主要な道具である。 全てのシナリオのすべての範囲について調査するために、気温と海面水位について高度な気候モデルと同じ応答をするように調整された簡便気候モデルを使用した。これらの予測結果は、7つの気候モデルと同じ気候感度と海洋の熱吸収量を持つように調整された簡便気候モデルによって得られている。ここで使用した簡便気候モデルの気候感度は1.7〜4.2℃の範囲で、広く容認されている1.5〜4.5℃という気候感度の範囲とほぼ一致する。 脚注(11):この気温の上昇量の不確実性には、放射強制力の予測に対する不確実性、例えばエーロゾルの強制力の不確実性等、は含まれていない。小さな炭素循環気候フィードバックは含まれている。 ・2100年まででは、ある一つのシナリオを用いて複数の気候モデルで計算した地上気温の予測による幅は、一つのモデルでさまざまSRESシナリオを用いて計算した気温の予測幅と同程度である。 ・現在観測されている気温上昇率は、気候感度に不確実性はあるとしても、ある排出シナリオの下で予測される応答の制約条件として、今後20〜30年は利用できる。この方法は、この先20〜30年は、IS92aシナリオの下では人為起源の温暖化が10年間に0.1〜0.2℃の範囲に入る可能性が高い(脚注7)ことを示唆しており、この範囲は、図5dで使われた簡便なモデルの予測幅とほぼ一致している。 ・最近の気候モデルによる予測では、ほとんど全ての陸域で地球の平均よりも早く気温が上昇し、特に北半球の高緯度で寒候期に顕著である可能性がかなり高い(脚注7)。顕著なのは、北アメリカの北部、アジアの北部と中央部での温暖化で、これらの地域では、地球の平均よりも40%以上の大きな温暖化が予測される。一方、夏のアジアの南部と南東部、冬の南アメリカの南部では、地球の平均よりも小さな上昇幅となる。 ・最近の海面水温のトレンドとして、太平洋熱帯域でエルニーニョ現象的な変化が強まり、海面水温は東部で西部よりも上昇量が大きくなり、これに伴って降水域は東へシフトしているが、多くのモデルで、これらのトレンドが続くと予測される。 (図5) 降水量 ・気候モデルのシミュレーションによると、シナリオの多くの場合に対して、地球の平均水蒸気量と平均降水量は、21世紀中は増加すると予測される。21世紀後半までに、北半球中・高緯度や南極で冬の降水量が増加する可能性が高い(脚注7)。低緯度の陸上では、増加する地域と減少する地域の両方がある。平均降水量の増加する地域の多くでは、降水量の年々変動も大きくなる可能性がかなり高い(脚注7)。 極端な現象 表1は、気象や気候の極端な現象について、20世紀後半に観測された変化(左欄)と21世紀に予測される変化(右欄)の信頼度を評価したものである(a)。この評価は、よく使われるシナリオの全てにわたる将来予測の物理的な妥当性だけではなく、観測データの解析やモデルの研究成果にも基づいており、さらに専門家による検討に基づくものである(脚注7)。 表1 極端な現象について、観測された変化と予測される変化の信頼度の見積もり |
| 観測された変化の信頼度 (20世紀後半) | 現象の変化 | 予測される変化の信頼度 (21世紀) |
| 可能性が高い(脚注7) | ほとんど全ての陸域で最高気温が上昇し、暑い日が増加する | 可能性がかなり高い(脚注7) |
| 可能性がかなり高い(脚注7) | ほとんど全ての陸域で最低気温が上昇し、寒い日、霜が降りる日が減少する | 可能性がかなり高い(脚注7) |
| 可能性がかなり高い(脚注7) | 大部分の陸域で気温の日較差が縮小する | 可能性がかなり高い(脚注7) |
| 多くの地域で可能性が高い(脚注7) | 陸域で熱指数(heat index:脚注12)が大きくなる | ほとんどの地域で可能性がかなり高い(脚注7) |
| 北半球の中・高緯度の陸域の多くで可能性が高い(脚注7) | 強い降水現象が増加する(b) | 多くの地域で可能性がかなり高い(脚注7) |
| 可能性が高い(脚注7)地域もある | 夏の大陸で乾燥しやすくなり、干ばつの危険性が増加する | 中緯度の大陸内部の大部分で可能性が高い (脚注7)(その他の地域では、一致した予測となっていない) |
| 入手可能なわずかな解析では観測されていない | 熱帯低気圧の最大風速が増大する(c) | いくつかの地域で可能性が高い(脚注7) |
| 評価するに十分なデータが存在しない | 熱帯低気圧の平均降水量と最大降水量が増加する(c) | いくつかの地域で可能性が高い |
|
a詳細は第2章(観測)、第9、10章(予測)を参照。 bその他の地域では、十分なデータが存在しないか、矛盾した解析結果が出ている。 c熱帯低気圧の位置や発生頻度についての、過去や将来の変化は不確実である。 脚注(12)熱指数(heat index)とは、人の快適さを評価する指数で、気温と湿度から求める。 ・その他の極端な現象に関しては、環境や社会に対して重要な影響があるものも多くあるが、現在のところ最近の傾向を評価するのに十分な情報がない。また、現在の気候モデルは、確実な予測を行うには空間解像度が不足している。例えば、雷雨、竜巻、ひょうや落雷などの非常に小さなスケールの現象は、気候モデルでは再現されていない。 エルニーニョ現象 ・熱帯太平洋におけるエルニーニョ現象の頻度、強度、空間的なパターンが将来どう変化するかを予測することは、高度なモデルの中でエルニーニョ現象をうまく再現できるかどうかという点が不十分なため、その信頼度は高くない。現時点では、この先100年間は、エルニーニョ現象の強度は、ほとんど変わらないか小さな増加にとどまると見込まれる。 ・エルニーニョ現象の強度はあまり変わらないか全然変わらないにしても、地球温暖化は、より極端な乾燥や大雨を増加させ、多くの異なった地域でエルニーニョ現象に伴って生じる干ばつや洪水などの危険性を増加させる可能性が高い(脚注7)。 モンスーン ・温室効果ガス濃度の増加に伴う温暖化で、アジア域の夏のモンスーンの降水量の変動は大きくなる可能性が高い(脚注7)。モンスーンの平均的な期間の長さや強度の変化は、排出シナリオによって異なる。このような予測の信頼度は、モンスーンの季節的な進行の細部が気候モデルでうまく再現できるかどうかによっても影響を受ける。 熱塩循環 ・大部分のモデルによると、海洋の熱塩循環が弱まり、そのため、北半球の高緯度への熱の輸送が小さくなる。しかしながら、たとえ熱塩循環が弱まったモデルでも、ヨーロッパは温室効果ガス濃度の増加のため温暖化する。気候モデルを使った現在の予測では、2100年までに熱塩循環が完全に停止することは示されていない。2100年以降、放射強制力の変化が十分大きく、かつ十分長期間にわたるとなると、熱塩循環はどちらの半球でも完全に停止し、再び循環が起きることはないと考えられる。 雪氷 ・北半球の積雪域や海氷域は、さらに縮小することが予測される。 ・氷河や氷帽は、21世紀の間、広範囲な後退が続くと予測される。 ・南極の氷床の質量は、降水量の増加によって増える可能性が高い(脚注7)。グリーンランドでは、降水量の増加よりも流出量の増加が大きいので、氷床の質量は減る可能性が高い(脚注7)。 ・西部南極氷床は、海面下で陸地に接しているので、その安定性が懸念されてきた。しかしながら、この氷床が融解することによって海面水位が相当上昇することが21世紀中に起こる可能性はかなり低い(脚注7)と現在では広く合意されている。ただし、氷床の力学は、特により長い時間スケールの予測に関して、まだ理解が十分でない。 海面水位 ・地球の平均海面水位は、SRESシナリオの全ての予測幅で、1990年から2100年までに0.09〜0.88m上昇すると予測される。この上昇の大部分は、熱膨張及び氷河と氷帽の融解による(図5e)。IS92シナリオに基づいた第二次評価報告書では、海面水位は0.13〜0.94mの上昇と予測されていた。今回の報告書で気温の変化予測が高くなったのに海面水位の上昇がわずかに低くなっている主な理由は、改良したモデルが使われ、そのモデルでは氷河や氷床の寄与が以前より小さく見積もられたからである。 人為起源の気候変化は、今後何世紀にもわたって続くと見込まれる・寿命が長い温室効果ガス(CO2、N2O、PFCs、SF6など)の排出は、大気組成、放射強制力及び気候に持続的な影響力を持つ。たとえば、二酸化炭素については、排出による濃度の増加量のおよそ4分の1が、排出後数世紀にわたって大気中に残留する。・地球の平均地上気温は、21世紀に濃度が安定化しないとして予測される100年あたり数℃の上昇に比べてかなり小さな値であるが、温室効果ガス濃度が安定化した後も、100年あたり0.2〜0.3℃の割合で上昇するであろう。濃度が安定化するレベルが低いほど、気温の総変化量は少なくなる。 ・深海が気候変化に適応する時間スケールが長いため、地球の平均地上気温の上昇と海洋の熱膨張による海面水位上昇は、温室効果ガスの濃度が安定したのちも数百年間続くと予測される(たとえ現在のレベルで安定化したとしても)。 ・氷床は、気候の温暖化に反応しつづけ、気候が安定したのち数千年間にわたって海面水位上昇の一因となり続けると見込まれる。気候モデルによると、グリーンランドでの局地的な気温上昇量は、地球全体の平均の1〜3倍になる可能性が高い(脚注7)。氷床モデルによると、もし、グリーンランドで気温が3℃以上高い状態が数千年続けば、グリーンランドの氷床は完全に融けて、海面水位が約7m上昇すると予測される。また、グリーンランドで気温が5.5℃高い状態が1000年続けば、グリーンランドの氷床融解により、約3mの海面水位の上昇がもたらされる可能性が高い(脚注7)。 ・現在の氷力学モデルは、西部南極氷床がこの先1000年間に3mの海面水位上昇をもたらし得ることを示唆しているが、この予測結果は、気候変化シナリオ、氷力学及び他の要因に関するモデル内の仮定によって大きく左右される。 さらに活動を重ね、気候変化に関する情報や理解の空白を埋めなければならない気候変化の検出、原因特定及び理解の能力を向上させ、不確実性を減らし、将来の気候変化を予測するために、さらに研究を進めることが必要である。特に、新規の組織的かつ持続的な観測と気候モデル及び気候の諸過程に関する研究が必要である。観測ネットワークの衰退が深刻に懸念されている。以下に、高い優先度を持つ実施分野を以下にあげる。・組織的な観測と過去の気候の復元 |
|
−世界の多くの地域における観測ネットワークの衰退傾向を反転させる。 −統合的地球観測のための戦略を実施することなど、正確で、長期の、一貫したデータを提供することにより、気候研究のための観測基盤を維持拡充する。 −過去の期間の気候の復元作業を進展させることを強化する −温室効果ガスとエーロゾルの空間分布の観測を改善する |
| ・気候モデルと気候の諸過程に関する研究 |
|
−放射強制力の変化をもたらす機構と因子の理解を改善する −高度なモデルを用いた長期アンサンブルシミュレーションなど、気候の予測とシナリオの不確実性を低減させる手法を改善する −気候システムの物理的及び生物地球化学的両面において、重要ながら未解明の諸過程やフィードバックを理解し特徴を明らかにする −気候変動、地域的気候変化及び極端な現象をシミュレーションすることを主眼に、統合的な階層構造を持つ全球気候モデル及び地域気候モデルを改良する −物理的な気候と生物地球化学システムのモデルをより効果的に関連させ、さらに人間活動の振る舞いとの結合を改善する |
|
これらの焦点の共通事項は、科学、計算機及び観測資源をより良く利用するために国際的な協力や調整を強化する必要性が極めて高いことである。科学者間の無料・無制限なデータ交換もまた促進すべきである。多くの地域、特に開発途上国において、観測及び研究に関わる能力を向上させることが特に必要である。おわりに、この評価報告書の目指すところでもあるが、研究の進展は、常に政策決定と係わる言葉で伝えられなければならない。 図 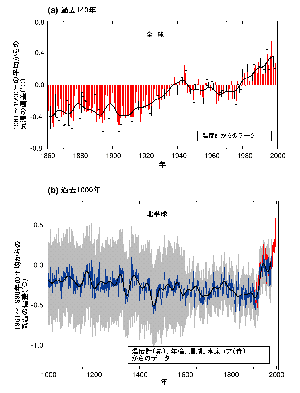 図1: 過去140年と過去1000年の地球の地上気温の変動 (a)地球の地上気温を年毎(赤棒グラフ)とほぼ10年平均(黒線、約10年以下の変動を除くためにフィルターをかけている)で示す。年々のデータには、データの不連続、機器によるランダムな誤差と不確実性、及び海面水温のバイアス補正や陸上における都市化の影響の補正における不確実性で生じる不確実性が含まれる(黒い縦線は95%の信頼区間を示す)。過去140年と100年の両期間ともに、最良の見積もりによると、地球の平均地上気温は、0.6±0.2℃上昇した。 (b)加えて、過去1000年間の北半球の地上気温の年々の値(青)と50年平均値(黒)の変動が、温度計によるデータに対して較正された「代替データ」(主な代替データは図中に示した)によって復元された。年々の値における95%の信頼区間が、灰色の領域によって示されている。これらの不確実性は、年代を溯るとともに増大し、また相対的にまばらな代替データを用いるため、観測機器による記録の信頼区間と比べて常に大きい。それにもかかわらず、20世紀の気温上昇の率と持続期間は、それ以前の9世紀のどれよりもかなり大きい。同様に、1990年代はこの1000年間で最も暖かい10年間であり、1998年は最も暖かい年であった可能性が高い(脚注7)。 [(a)は第2章図2.7c、(b)は第2章図2.20に基づく] (本文へ戻る) 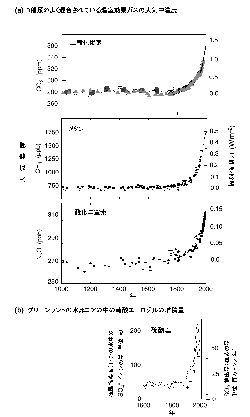 図2 過去の大気組成の変化に関する長期間にわたるデータから、人為起源による排出の影響に関するおおまかな状況がわかる。 (a)は、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O)の大気中濃度の過去1000年にわたる変化を示す。南極及びグリーンランドのいくつかの観測点における氷床コア及び万年雪から得られたデータ(図中に別々の印で示す)に最近数十年間に大気を直接測定して得られたデータを加えて示す(二酸化炭素では、直線で直接測定部分を示し、メタンでは、地球の平均を曲線で表す)。これらのガスが気候システムに及ぼす正の放射強制力の見積もりを右側の軸に示す。これらのガスの大気中における寿命は10年以上であることから、大気中でよく混合されており、その濃度は地球全域からの排出量を反映する。これら3種類のデータにより、産業革命以降の工業化時代における人為起源の排出量の大幅な増加による影響が分かる。 (b)は、産業活動による排出が大気中の硫酸エーロゾル濃度に及ぼす影響を示している。硫酸エーロゾルは、負の放射強制力を持つ。図に示されているのは、大気中ではなくグリーンランドの氷床コアの中の硫酸塩濃度の時間変化である(図中に線で示す。ただし、火山噴火による一時的な影響は除去してある)。このデータから、グリーンランドでの局所的な硫酸エーロゾルの堆積量は、北半球中緯度の二酸化硫黄(SO2)の排出量を反映していることが分かる。また、全地球的によく混合されている温室効果ガスに比べて地域的な側面が強いにもかかわらず、産業革命以降の人為起源の二酸化硫黄の排出量が大きく増加している様子が示されている。 +の記号は、地域的な二酸化硫黄排出量を示している(右側の軸)。[(a)については、第3章図3.2b(CO2)、第4章図4.1a及びb(CH4)、第4章図4.2(N2O)、また(b)については、第5章図5.4aをそれぞれ基に作成。] (本文へ戻る) 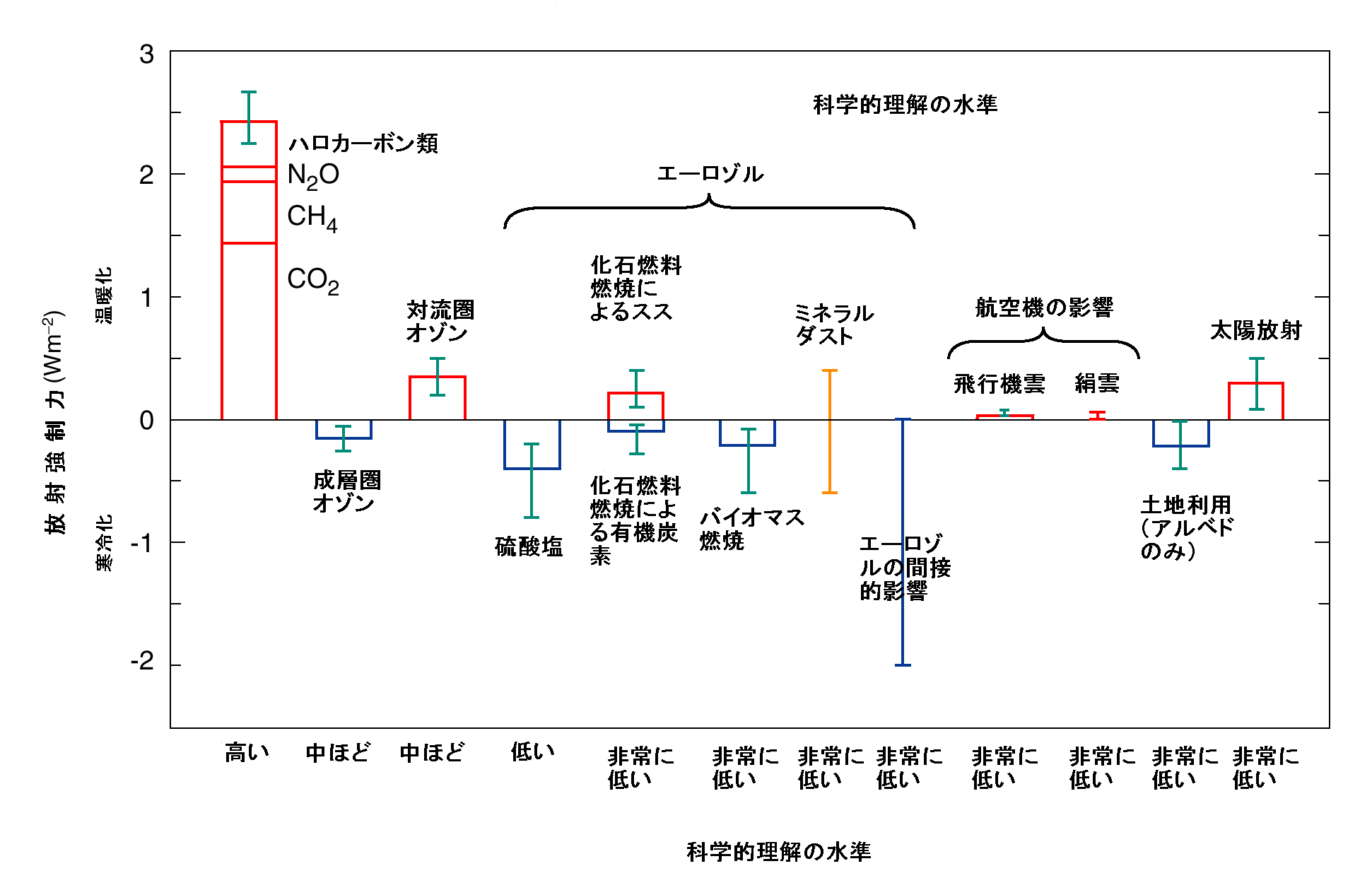 図3:気候変化を起こす多くの外部因子 これらの放射強制力は、大気組成の変化、土地利用による表面反射率の変化、及び太陽放射の変動によって起こされる。太陽放射を除いて、人間活動が何らかの形でそれぞれに関連している。棒グラフは、これらの放射強制力の寄与の見積もりを表す。あるものは温暖化、あるものは寒冷化をもたらす。一時的な火山噴火による放射強制力は、数年しか続かない負の値の放射強制力なので、図には示されていない。 図中のエーロゾルの間接的効果は、それらが雲粒の大きさと数に及ぼす影響である。雲に対するエーロゾルの2番目の間接的効果は、すなわち雲の寿命への影響で、それは負の値の放射強制力をもたらすが図には示されていない。温室効果ガスへの航空機の影響は個々の棒グラフに含まれている。それぞれの棒グラフに付された縦線は見積もりの幅を示し、放射強制力の公表値や物理学的解釈の違いに基づくものである。 放射強制力のいくつかは他と比べてかなり信頼性がある。棒グラフのない縦線は、不確定性が大きいために最良の見積もりが得られないものである。図中に示されているように、おのおのの放射強制力に対する科学的理解を見ると、全体としてはかなりばらついている。いくつかの放射強制力要因は、二酸化炭素のように地球全体でよく混合されているため、地球全体の熱収支を変動させる。他のものは、エーロゾルのように、その空間的な分布のため、より強い局地的な影響を伴った変動を示す。これら及び他の理由により、正負の棒グラフを単純に合計して、正味で気候システムにどのような影響をもたらすかを考えることはできない。この評価報告書のためのシュミレーション(例えば、図5)は、これらの変動に関して見積もられた正味の影響が、1750年以降、地球の気候を温暖化してきたことを示す。[第6章図6.6に基づく] (本文へ戻る) 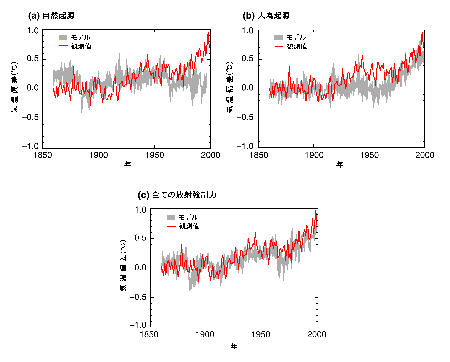 図4 地球の気温の変動を再現し、再現結果を観測された変化と比較することにより、主な気温変化の原因を見きわめることができる。 気候モデルは自然起源の原因と人為起源による原因の両者によって生ずる気温変化を再現するのに利用できる。(a)の帯で示すシミュレーション結果は、太陽放射と火山噴火による自然起源の放射強制力だけで得られたものである。(b)の帯で示すものは、人為起源の放射強制力(温室効果ガスと硫酸エーロゾルの見積り)、(c)の帯で示すものは自然及び人為起源の放射強制力双方を与えて得られたものである。(b)からは、人為起源の放射強制力を用いることで、過去100年間の観測された気温変化の大部分をもっともらしく説明することが読みとれるが、観測データと最も合うのは、自然起源の因子と人為起源の因子の両者を組み入れた(c)で得られる。これらの結果は、ここで考慮した放射強制力が、観測された気温変化を十分説明していることを示しているが、これ以外の放射強制力も寄与している可能性を排除するものではない。ここで示したシミュレーション結果の幅は同一の気候モデルを用いた4つの実験によるものである。(b)と同様の結果は、人為起源の放射強制力を与えた他の気候モデルでも得られている。[第12章図12.7に基づく] (本文へ戻る) 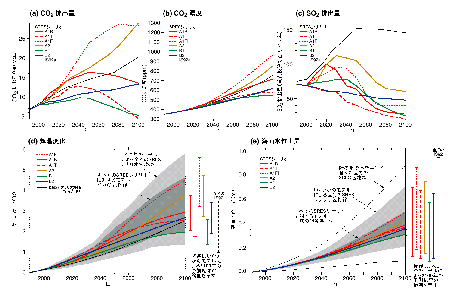 図5 21世紀の地球の気候は、自然の変化と気候システムの人間活動に対する応答で決まることになる。気候モデルは、温室効果ガスやその他の人間活動に関係する排出の種々のシナリオに対する多くの気候変数の応答−地球の地上気温や海面水位の上昇−を予測する。(a)には、代表例として用いられた6個のSRESシナリオの二酸化炭素排出量を示しており、これらについては下のボックスに第二次評価報告書との比較のためIS92aとともに要約してある。(b)は、二酸化炭素濃度の予測を示す。(c)は、人為起源の二酸化硫黄の排出量を示す。 その他のガス及びその他のエーロゾルの排出量も気候モデルに含まれているが、図には示してない。 (d)と(e)は、それぞれ、気温上昇と海面水位上昇の予測を示す。(d)と(e)の「いくつかのモデルによる全てのSRESシナリオ包絡線」は、ある範囲の気候感度を持つ多数の高度な気候モデルで調整した簡便な気候モデルによる気温と海面水位上昇それぞれを示す。 「全てのSRES包絡線」は、全35個のSRESシナリオによる範囲を表している。「すべてのSRESシナリオに対するモデル平均の包絡線」は、シナリオの範囲に対するモデルの平均を表している。これらの排出による気温上昇と海面水位上昇の双方とも2100年のずっと先まで続くことに注意されたい。また、ここで示した範囲は、西部南極氷床の氷の力学的変化に関係した不確実性は考慮していないこと、また、硫酸エーロゾル以外のエーロゾルや温室効果ガスの濃度の予測の不確実性も考慮していないことにも注意されたい。[(a)は第3章図3.12、(b)は第3章図3.12、(c)は第5章図5.13、(d)は第9章図9.14、(e)は第11章図11.12、付録2に基づく] (本文へ戻る) |
|
排出シナリオに関する特別報告(SRES)の排出シナリオ A1. A1の筋書きとシナリオファミリーは、高度経済成長が続き、世界人口が21世紀半ばにピークに達した後に減少し、新技術や高効率化技術が急速に導入される未来社会を描いている。主要な基本テーマは、地域間格差の縮小、能力強化(キャパシティービルディング)及び文化・社会交流の進展で、1人あたり所得の地域間格差は大幅に縮小するというものである。A1シナリオファミリーは、エネルギーシステムおける技術革新の選択肢の異なる三つのグループに分かれる。この三つのA1グループは技術的な重点の置き方によって以下のものに区別される。すなわち、化石エネルギー源重視(A1FI)、非化石エネルギー源重視(A1T)、そして全てのエネルギー源のバランス重視(A1B)である。(ここで、バランス重視は、いずれのエネルギー源にも過度に依存しないことと定義され、全てのエネルギー供給・利用技術の改善度が同じと仮定している) A2. A2の筋書きとシナリオファミリーは、非常に多元的な世界を描いている。基本テーマは独立独行と地域の独自性の保持である。出生率の低下が非常に緩やかなため、世界の人口は増加を続ける。地域的経済発展が中心で、1人あたりの経済成長や技術変化は他の筋書きに比べバラバラで緩やかである。 B1. B1の筋書きとシナリオファミリーは、地域間格差が縮小した世界を描いている。A1筋書きと同様に21世紀半ばに世界人口がピークに達した後に減少するが、経済構造はサービス及び情報経済に向かって急速に変化し、物質志向は減少し、クリーンで省資源の技術が導入されるというものである。経済、社会及び環境の持続可能性のための世界的な対策に重点が置かれる。この対策には公平性の促進が含まれるが、新たな気候変動対策は実施されない。 B2. B2の筋書きとシナリオファミリーは、経済、社会及び環境の持続可能性を確保するための地域的対策に重点が置かれる世界を描いている。世界の人口はA2よりも緩やかな速度で増加を続け、経済発展は中間的なレベルに止まり、B1とA1の筋書きよりも緩慢だが、より広範囲な技術変化が起こるというものである。このシナリオも環境保護や社会的公正に向かうものであるが、地域的対策が中心となる。 6つのシナリオグループの各々について、1つずつ例示シナリオA1B、A1F1、A1T、A2、B1、B2を選んだ。どれも同等の根拠を持っていると考えるべきである。SRESシナリオは追加的な気候変動対策を含んでいない。すなわち、いずれのシナリオも気候変動枠組み条約や京都議定書の削減目標が履行されることを明示的に仮定していない。 |